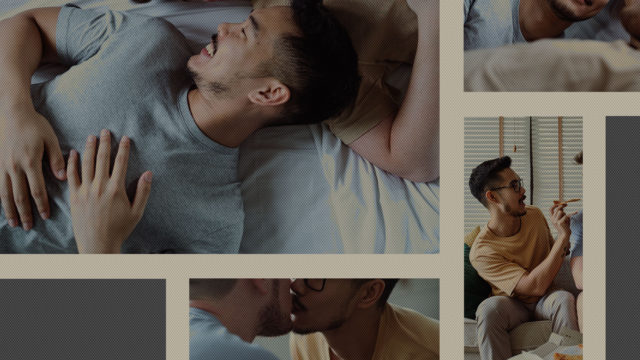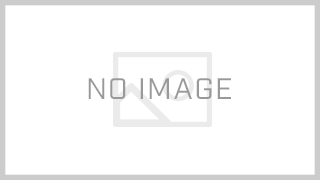- Sindbad Bookmarksの閉鎖に寄せて、これまでとこれからを振り返る
- 1990年・ゲイ雑誌が果たしていた役割
- 1996年・Sindbad Bookmarks・Mens Net Japanが登場し、情報が「整理された」時代に
- 1990年後半・Geocities・夜のインターネット漂流記
- 2000年代初頭・魔法のiらんど・ガラケー文化と感情の置き場所
- 2000年代初頭・2ちゃんねる同性愛板・毒と共感が交差する場所
- 2004年・mixi・趣味でつながることの温かさ
- 2009年・Grindr・ゲイアプリを使うためにiPhoneを買う
- 2010年以降・ゲイアプリの時代・出会いの最適化、孤独の再生産
- 2020年代・Twitter・すべてがある、だからこそ過酷な場所
- 2025年以降・これからゲイたちは、どうやって「情報」と付き合っていくのか?
- 変わるのは手段であって、本質ではない
Sindbad Bookmarksの閉鎖に寄せて、これまでとこれからを振り返る
2025年8月1日、長年ゲイ文化を支えてきたリンク集サイト「Sindbad Bookmarks」が静かに閉鎖された。
https://www.sindbadbookmarks.com/
1996年に開設されて以来、およそ30年にわたり、ゲイの情報収集と、コミュニケーションの基盤を支えてきたこの存在は、単なるリンク集以上の意味を持っていた。
インターネットが一般に普及する以前、ゲイであるということは「何も情報がない」こととほぼ同義だった。
何が普通で、どう出会い、どう語るべきか。
誰にも聞けず、誰も教えてくれない。
だからこそ、雑誌の1行、個人サイトのエッセイ、BBSの書き込み、アプリの自己紹介まで、
すべてが「生きるためのヒント」でありゲイの出会いのために必要なものだった。
ここでは、雑誌から始まり、Geocities、魔法のiらんど、Mens Net Japan、2ちゃんねる、mixi、アプリ、Twitter、AIの時代に至るまで、
ゲイたちがどのようにして情報を集め、出会い、自分自身を知ってきたのかを丁寧に振り返り、そのうえでこれからの未来を、慎重に、しかし前向きに予測する。
1990年・ゲイ雑誌が果たしていた役割
インターネット以前、多くのゲイにとって最初の情報源は雑誌だった。
『薔薇族』『さぶ』『G-men』『Badi』など、ゲイ向け雑誌は、グラビアだけでなく、読者投稿、体験談、相談コーナー、イベント案内など、生活と文化のすべてが詰まっていた。
誰にも言えないことが、そこには書かれていた。
地方に住むゲイにとって、「自分以外の誰かがこの国のどこかで同じように生きている」という確信を得られる唯一のツールだった。
1996年・Sindbad Bookmarks・Mens Net Japanが登場し、情報が「整理された」時代に
1996年にSindbad Bookmarksは登場し、個人サイト・出会い系・情報系・エッセイなどを分類整理したゲイリンク集の金字塔だった。
毎晩巡回して、新着サイトを確認する。
それは、まだ見ぬ誰かに会いにいく行為だった。
また同時期に、MNJ(Mens Net Japan)が生まれた。
全国のゲイバー、サウナ、ハッテン場、イベント情報などを整理して掲載。
地方のゲイにとっては、「東京に行ったら、ここに行けばいい」という羅針盤になった。
派手さはないが、実用性と信頼性で長く使われ続けた情報の基盤で、現在もゲイ情報を取得する主流サイトとなっている。
1990年後半・Geocities・夜のインターネット漂流記
1990年代後半、家庭用インターネットが普及し始めると、ゲイたちは個人ホームページを通じて自己表現を始める。
Geocitiesは、その代表格だった。
HTMLで手作りされた日記、プロフィール、掲示板、リンク集。
自己紹介には「ゲイです」と明言しないまでも、「似た人」が確かにそこにいた。
深夜、リンクを辿って旅をする感覚。
それは孤独を少しだけ照らしてくれる行為だった。
2000年代初頭・魔法のiらんど・ガラケー文化と感情の置き場所
ガラケーで流行したのが魔法のiらんど(魔i)。
元々は女子中高生のポエムや恋愛日記の場だったが、若いゲイたちも利用していた。
プロフ、ポエム、裏日記、掲示板。
そこでは「恋してるけど、誰にも言えない」「誰かに話を聞いてほしい」といった感情が静かに交わされていた。
出会いよりも、誰かに気持ちを届けたいという欲望が強かった時代である。
2000年代初頭・2ちゃんねる同性愛板・毒と共感が交差する場所
同性愛板は、すべてのゲイが匿名で語れる場だった。
ノンケへの片想い、老い、性癖、裏事情、差別。
雑誌にも日記にも書けなかったことを、ここでは吐き出すことができた。
鋭く冷たいコメントもあれば、優しさやユーモアもあった。
人間の生々しさが、ここには詰まっていた。
2004年・mixi・趣味でつながることの温かさ
2004年以降にmixiが登場して、ゲイたちは匿名性とSNSのあいだで揺れながらも、マイミク・日記・コミュニティを使いこなした。
「ノンケに片想い中」「ガチムチ好き同盟」「地方ゲイサバイバル」など、似た人が集まる場=安心できる場となった。
2009年・Grindr・ゲイアプリを使うためにiPhoneを買う
2009年、Grindrが登場。
GPSで近くのゲイが表示されるという画期的な仕組みに、多くのゲイが驚いた。
そして、「グラインダーを使いたいからiPhoneを買う」ゲイが急増した。
出会いは探すものから、表示されるものへと変わった瞬間だった。
2010年以降・ゲイアプリの時代・出会いの最適化、孤独の再生産
Grindrの後、9monsters、Jack’d、Hornet、BLUEなどが次々登場。
- 見た目
- ポジション
- 年齢
- 筋肉量
- 趣味
すべてがタグになり、出会いはスペック重視に。
一方で、「選ばれない側」の孤独もまた拡大していった。
2020年代・Twitter・すべてがある、だからこそ過酷な場所
2020年代、ゲイの主戦場は完全にTwitter(X)になった。
裏垢、鍵垢、リスト文化、エロ、愚痴、恋愛、広告。
すべてが同じタイムラインに並び、誰かの声がすぐそばにあるようで、誰の声も届かないこともある。
匿名性が守ってくれることもあれば、晒し文化に傷つくこともある。
それでも、ここには確かに「情報」と「生」がある。
2025年以降・これからゲイたちは、どうやって「情報」と付き合っていくのか?
1. AIが探さなくても届く時代をつくる
AIによる情報のパーソナライズは、今後さらに進化する。
「あなたが好きそうなAV男優」「気分に合ったゲイバー」「性癖が一致しそうな相手」など、感情と嗜好に合わせたレコメンドが標準化される。
ただし、視野の狭まりや偶然性の喪失というリスクもある。
2. 匿名と実名のあいだで、ゆらぐ自分を演出する
鍵垢、裏垢、匿名SNS、オープンチャットなど、複数の人格を使い分ける文化が主流になる。
実名では言えないことを、仮名で安心して言える場。
SNSは全人格をさらすものではなく、必要な人格だけを見せる時代へ。
3. 情報の発信地は分散していく
今後はXの一極集中から、情報が分散する時代へ。
- 小規模なゲイブログや匿名掲示板の復権
- イベント、Podcast、ニュースレターなどのパーソナルメディア化
が再定義されて、それぞれの文化圏ごとに情報の温度も変わる事が予測される。
4. コミュニティは避難所になる
コミュニティ文化は衰退どころか、再定義されて復活する。
「共通の苦しみ」「共通の好み」「共通の孤独」を共有するコミュニティは、閉鎖的に見えて、実は開かれたケアの場になる。
5. 実際に会うことが意味を持つ時代に戻る
デジタルが進化すればするほど、身体性への欲求が戻ってくる。
- 少人数オフ会
- リアルな語り合い
- 触れる・見る・空気を読む
人と人の存在感が再び大切にされるだろう。
変わるのは手段であって、本質ではない
ゲイにとって、情報を探すとは、自分の存在を確認することだった。
それはこれからも変わらない。
どんなにAIが進化しても、ゲイアプリが洗練されても、SNSが分散しても、「誰かに届いてほしい」という気持ちだけは、変わらず残り続けるだろう。
そしてゲイたちはまた、次の時代の情報の中で、新しい自分を見つけ出していくだろう。